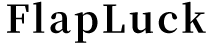6月が旬のおすすめ果物・フルーツ7選!日持ちする方法も解説

果物・フルーツはお好きですか?
6月は旬をむかえる果物が沢山あります。
年中スーパーで見かける身近な果物から、中にはこの時期しか味わえないものまでご紹介!果物は食べたいけど名かなか買う機会がなくて・・・という方も、この記事をみたら今すぐ買いに行きたくなってしまうこと間違いなし!
果物は美味しいだけでなく、実は栄養価も豊富。
今回はそんな6月に旬を迎える果物の中からおすすめ7選をご紹介!
あなた一押しの果物はどれですか?
↓旬の野菜を美味しくする無水調理鍋↓


メロン
メロンの栄養素

メロンにはビタミンCやカリウム、たんぱく質分解酵素といった栄養素が含まれています。
ビタミンCはシミの原因となるメラニンの生成を抑える効果の他、抗酸化ビタミンとして抵抗力を高め、風邪やストレスに強い身体づくりにも役立っています。
カリウムは余分な塩分を体の外に追い出してくれるので、むくみ改善や高血圧予防に効果的な栄養素です。
また、「ククミシン」というたんぱく質分解酵素はお肉や魚に含まれるたんぱく質を分解してくれるため、お肉が硬い場合はメロンをミキサーにかけた漬け汁に漬けてから焼くと柔らかく仕上がります。
おいしいメロンの選び方

熟しているメロンは甘い香りが漂っていたり、お尻の部分をさわると少し弾力を感じます。
また、つる付きの場合T字の細い方のツルが少ししおれていると食べ頃。つるがみずみずしくピンと経っている物はまだ完熟していません。
購入後1~2日で食べるならほぼ完熟に近い物を選びましょう。数日後に食べるなら果肉がかための物を購入し、涼しい所で追熟させればOKです。
メロンの日持ちする方法
食べごろまでは涼しい場所で保管、食べ頃になったら冷蔵庫にしまい早めに食しましょう。
未熟なメロンを冷蔵庫に入れてしまうと追熟が止まってしまうため、食べ頃になる前は必ず常温保存で風通しの良い日陰で保管、高温多湿を避けるようにしてください。
ブルーベリー
ブルーペリーの栄養素

ブルーベリーは小さな実ですが、アメリカではスーパーフードの一つに数えられる事があるほど実は栄養素が豊富。
ビタミンCをはじめ、ビタミンE、食物繊維、ミネラル、アントシアニンなどの栄養素が含まれています。
ビタミンCはコラーゲンの生成を助ける働きがあり、しわ予防に効果的。
ビタミンEは抗酸化作用があるので、ビタミンCと共に、シミ予防に役立ちます。
ミネラルは鉄分や亜鉛、マンガンが特に多く含まれていて貧血予防や細胞代謝を促したり、骨を丈夫にしたり活性酸素を除去する働きがあります。
このようにブルーベリーは肌を整え、骨を丈夫にする栄養素が多く含まれている事からブルーベリーはアンチエイジング効果が高いと評価される事もあります。
果皮や赤肉の青色は主にシアニジンなどのアントシアニンと呼ばれるポリフェノールが含まれています。
このアントシアニンは強い抗酸化作用を有しブルーベリーはベリー類の中でもトップクラスの含有量を有します。
夜間視力の向上、緑内障の予防に加え、眼精疲労の軽減など目の機能改善に効果的と言われています。
おいしいブルーペリーの選び方

ブルーベリーを選ぶ際は色味をチェックします。
皮の色が濃く鮮やかな青紫色の物、張りのあるものが新鮮な証拠です。
しわが寄って柔らかくなっている物は鮮度が落ちている可能性が高いので避けましょう。
また、ブルーベリーの表面についている白い粉は「ブルーム(果粉)」と呼ばれ、果実の表面を保護し、乾燥を防ぐ役割があります。完熟した新鮮な果実程多いにでおいしさのサインになります。
また、ブルーベリーは青く色づいたあとにもう一回り成熟する果物・フルーツのため、比較的大粒な物が甘い果実です。
粒が小さいほど渋みが強くなりますが、その分ポリフェノール含有量は多くなります。
ブルーベリーの日持ちする方法
ブルーベリーを保存する際は乾燥を防ぐことが大切です。
冷蔵保存する場合は傷んだ実を避け、キッチンペーパーで包み、冷蔵庫の野菜室で約一週間保存可能です。
冷凍する際は水洗いして水気をしっかり拭き取り、小分けにしてジップロック袋で約半年保存できます。
さくらんぼ
さくらんぼの栄養素

さくらんぼは小さい粒の中にバランス良く栄養素を含んだフルーツです。
特徴的な成分としては葉酸、ブルーベリーと同じくビタミンCやアントシアニンがあげられます。
中でも葉酸はビタミンB12とともに赤血球を作るため、「造血ビタミン」とも呼ばれ、特に妊娠初期に胎児の神経管閉鎖を助け、脳や脊髄の正常な発育に不可欠な成分とされています。
おいしいさくらんぼの選び方

さくらんぼは追熟しないので、青みが残っている物ではなくしっかりと紅く色づき、鮮やかで艶があるものがお勧めです。
部分的に茶色っぽく変色したり傷がついている物や枝が茶色くなっているものは鮮度が落ちていた李食べごろを過ぎている事があるため、購入は控えるようにしましょう。
さくらんぼの日持ちする方法
さくらんぼは収穫と共にどんどん味が落ちていきます。買ったらすぐにたべるようにしましょう。数日であれば新聞紙などにくるんで野菜室で保存すると少し長持ちします。
夏みかん
夏みかんの栄養素

夏みかんは柑橘類の中でも糖分が少ない分、カロリーも控えめで美肌効果があるビタミンCや疲労物質である乳酸を分解し疲労回復に効果があるとされるクエン酸、むくみ予防に効果的なカリウムなどのミネラル類が含まれています。
また独特の苦みはフラボノイド類の「ナリンギン」という成分によるもので抗酸化活性や抗炎症作用があると言われています。
おいしい夏みかんの選び方

夏みかんは皮に張りがあり、同じ大きさであればずっしりと重みを感じるものをえらびましょう。
持った時に軽く感じる者は水分が減っている事があります。
また、ヘタが茶色くなっていたり取れてしまっている物などは避けましょう。
夏みかんの日持ちする方法
夏みかんは涼しい冷暗所で保存します。状態にもよりますが1~2週間を目安になるべく早めに消費してください。
「夏みかんは酸っぱい」というイメージがあるかもしれませんが、酸味が強い場合は常温に数日置いておくと酸味が徐々に抜けていきますので調整してみてください。
びわ
びわの栄養素

びわに含まれるβカロテンは強い抗酸化作用を持ち、活性酸素の発生を抑制し取り除く働きを持っています。
活性酸素は体内に入ってきた細菌やウイルスを退治する働きがあり、微量であれば人の身体にとって有益です。
しかし過剰になると過酸化脂質を作りだし、動脈硬化や免疫力の低下をまねく事がありますので適度に取り入れたい成分です。
また体内で必要に応じで皮膚や粘膜を守る働きがあるビタミンAに変換され喉や鼻の健康を保つのに役立ちます。
同じくびわに含まれるβクリプトキサンチンは骨粗鬆症のリスクを軽減する効果が期待できるとされており、古くなった骨を壊す「骨吸収を抑制すると共に骨形成を促し骨密度や骨代謝を改善する作用が報告されています。
βクリプトキサンチンもβカロテン同様体内で必要に応じビタミンAに変換されます。
他にもポリフェノールの一種であるクロロゲン酸やカリウムなどのミネラルも含まれます。
おいしいびわの選び方

びわ特有のきれいなオレンジ色をしていて表面に傷や茶色く変色した部分がない物、果皮に張りのあるもの、ヘタがしおれていない物を選びましょう。
またびわの表面には産毛が生えていて、この産毛がしっかり生えているかどうかが鮮度の目安医になります。
産毛が薄くなっていたりとれていたりするものは鮮度が落ちている可能性が高いのでさけましょう。
表面に白い「ブルーム(果粉)」が付いているものは新鮮でかつ完熟した証拠でおいしさのサインになります。
びわの日持ちする方法
全体がふっくらと張りがあり、左右対称で表面に産毛が密生しているものが新鮮な証です。
また、皮が鮮やかなオレンジ色でツヤがあり軸がしっかりしている物が良いとされています。
びわは非常に傷みやすく追熟しておいしくなるものでもありませんので、新鮮なものを購入しすぐに食べるようにしましょう。
いちじく
いちじくの栄養素

いちじくは栄養価が高く「不老長寿の果物」とも呼ばれています。
特に強い抗酸化作用を持つビタミンE、たんぱく質の成分である「アミノ酸」の代謝に関わり皮膚や神経を正常に保つ働きのあるビタミンB6や、造血ビタミンとして知られる葉酸が含まれます。
他にも体内の過剰な塩分(ナトリウム)を排泄し、高血圧予防やむくみ解消に効果的なカリウム、歯や骨の健康を守り、筋肉から神経の働きを正常に保つ働きのあるカルシウム、その他マグネシウムや銅などのミネラル類が豊富です。
さらにはアントシアニンというポリフェノールが皮の部分に多く含まれていたり、フィシンというたんぱく質分解酵素のおかげで消化を助けてくれる効果も期待できます。
食物繊維もしっかり含まれるいちじくはまさにスーパーフードですね。
おいしいいちじくの選び方
いちじくは熟すと果皮が赤褐色になるので、なるべく全体が色づいている物を選ぶようにしてください。緑色が目立つものは果肉が硬かったり甘みが薄い事があります。
また、いちじくの先端に少し割れ目があるものが完熟のサインになります。過度に割れている物はは熟しすぎなので避けた方がいいでしょう。
鮮度の証としてもぎたてのいちじくは切り口から白い液が出てきます(作者は実家にいちじくの樹があったのでもぎたてを食べていました)。

そして新鮮なものは果皮に張りがあり、果肉もしっかり弾力がをありますが、時間が経つにつれ果皮は弾力をなくし、果肉が柔らかくなってしまいます。
いちじくは鮮度が命なので購入したらその日のうちに食べましょう。
いちじくの日持ちする方法
いちじくは基本的に熟した状態で収穫しています。また傷みやすいので購入したその日に食べるようにしましょう。
食べきれない場合は一個ずつラップで包み冷蔵庫の野菜室で2~3日を目途に食べきりましょう。
梅
梅の栄養素

梅は果物ですが、他の果物と異なり、梅干しや梅酒、梅ジャム等加工して食すのが一般的です。
梅は果物の中でもミネラルやビタミンが豊富です。特にりんごと比べ、カリウムは約2倍、カルシウムは4倍、鉄は6倍、ビタミンEは33倍も豊富に含まれています。
骨や歯、血液など人間の体を形成しているものの中には鉱物性の栄養素(ミネラル)が含まれ、カルシウムや鉄もその一つです。
カルシウムや鉄は一般的に吸収率の低い栄養素ですが、梅に含まれるクエン酸にはこれらカルシウムや鉄の吸収を促しカルシウムが骨から持ち出されるのを防ぐ働きがあるとも言われ、骨粗鬆症や貧血予防にも効果的です。
おいしい梅の選び方
お店には硬い青梅や完熟した黄色い梅が売られていますが何を作るかによって色やかたさを選びましょう。
いずれの場合も果肉がふっくらとしてきれいな丸みがあり、表面に傷や斑点がないもの、また果皮に張りがあるかがポイントです。

・やわらかい梅干しや梅ジャムを作るならある程度熟した黄色い果実がおすすめ。
程よく熟した梅で梅干しを作ると口当たりのよいソフトな梅干しができます。ただしやわらかすぎるものは傷んでいる事があるので避けた方が無難です。

・かための梅干しにするなら、青みが残る物を、またカリカリ梅を作るなら青みがかった梅が最適です。

・梅酒や梅シロップには、かための黄緑色の梅が使われる事が多いですが、果実にかたさがあれば黄色い梅でも大丈夫。
ただし完熟したやわらかい梅を使うと濁りやとろみが出る事があるので気を付けてください。
梅の日持ちする方法
果肉のやわらかい黄色い梅は、購入したら早めに加工しましょう。
そのままおいておくと更に柔らかく傷みやすくなってしまいます。
青みがかった梅干しは、カリカリ梅にしないのであればそのまま常温で置いておくと数日で黄色くなってくるので、自分の作りたい物に応じて使う時期を見極めるといいですね。
6月が旬のおいしい果物を堪能しよう
いかがでしたでしょうか。
紹介した果物の中にはびわや梅、いちじくなどこの時期にしか市場に出回らず、旬を逃すと味わえない物も多いです。
年間通して出回る果物もありますが、やはり旬の時期が一番おいしくかつ栄養も豊富です。
買い物に行かれた際には是非旬の果物も一緒に手に取ってみてはいかがでしょうか。
果物と同様、6月には初夏から夏に旬を迎える夏野菜も目白押し!野菜は果物同様そのまま食べても良いものから、加熱する事で旨味を増すものもあります。
加熱の際はお鍋で茹でたり、フライパンで焼いたりする事が多いかと思いますがお勧めは蒸し野菜!無水調理鍋なら、余分な水を使わずに加熱ができるので、旬の野菜の旨味を存分に引き出すことができますよ。
野菜をおいしくする無水調理鍋は一家に1個あるととても便利です。
軽量でお手入れをしやすく清潔感が保ちやすい無水調理鍋、数量限定で好評発売中です。