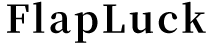5月と6月が旬の魚7選!鮮度の良い魚の見分け方

春から初夏を迎えるこの時期、お店に並ぶ魚にも季節を感じます。
4月、春先の魚としてカツオやブリを紹介しましたが、今回は主に5月と6月におすすめの魚7選をピックアップ。
その他旬の貝類もご紹介!あなたが食べたい魚介類もきっと見つかるはず。
是非参考にしてください。
どれも栄養価満点。そして旬の食材は味わい深く是非多くの方に積極的にとりいれていただきたいものです。
↓↓数量限定!魚介類を更に美味しくする無水調理鍋はこちら↓↓


鰆(サワラ)
サワラの栄養素

サワラはサバの仲間で、大きくなると1ⅿ以上まで成長します。
様々な調理法で食べられる魚で青魚に分類されます。サワラをはじめ、青魚に豊富に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)はオメガ3脂肪酸のひとつで、悪玉コレステロールや中性脂肪の低下をはじめ、生活習慣病予防の一助になると考えられています。
EPA(エイコサペンタ塩酸)もDHAと同じくオメガ3脂肪酸の一種で、動脈硬化予防に効果的です。
他にも糖質やたんぱく質、脂質を体内でエネルギーに変え、疲労回復に役立つビタミンB2、味覚の働きを正常に保ち、皮膚や粘膜の健康維持に役立つ亜鉛、そして、体内のナトリウムとのバランスをとり、高血圧予防やむくみ予防にもなるカリウムを豊富に含んでいます。
新鮮なサワラの見分け方
サワラは切り身で買うことが多いと思います。
サワラは痛みが早い魚ですので、切り身を選ぶ際は身の色を確認し、透明感のあるものを選ぶようにしましょう。
鮮度が落ちるとすぐに白く濁ってしまいます。
また身割れがしやすいので、身が割れていないもの、血合いの部分がなるべく鮮やかなものを選びましょう。
サワラの勧めの食べ方

新鮮なサワラが手に入ったら、是非刺身で味わってみてください。皮つきの場合は軽く皮を炙るのもおすすめ!
水分が多く柔らかい魚なので、薄切りにしてしゃぶしゃぶにしたり、焼いても硬くなりにくいので漬け込んで西京漬けにするとおいしく召し上がれます。
さわらのさっぱりとしたおいしさを味わいたいのであれば、シンプルに塩焼きもおいしいです。
鯵(アジ)
アジの栄養素

アジはサワラと同じく青魚の一種です。
そのため、DHA、EPAといった、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。
また、アジは高タンパク質な魚でありますので、ダイエット中でも安心して食べる事が出来、健康的な体作りにお勧めのお魚です。
さらにはカルシウムの吸収を助け、骨を強くするビタミンDも豊富に含まれているので、成長期のお子さんや高齢者の方には是非とってもらいたい食材です。
新鮮なアジの見分け方と保存方法
アジ全体を見た時にピンと身体全体に張りがあるもの、皮の色が鮮やかで金属的な光沢があるもの、目を見て黒目は黒々として、透明な部分は濁りがなく澄んでいるものを選びましょう。
また小顔に見えるアジは身体に脂がのっている証拠。
小顔に見えるアジは身体の頭から背中、おなかの部分が太って厚みが増し脂がのっているので丸々1尾で選ぶときは参考にしてみてください。
アジのお勧めの食べ方

アジは「味がいいからアジ」と名付けられたと言われるほど旨味成分のイノシン酸が豊富に含まれていて、生でも加熱してもおいしいです。
アジはお寿司やお刺身、なめろうといった生食だけでなく、アジフライやムニエルなども人気です。
しかし、アジに限らず魚に含まれるEPA、DHAという脂質は、酸化されやすく特に熱を加えると劣化します。新鮮な魚が手に入った際には是非生のまま食べてみてください。
しらす
しらすの栄養素

通常「しらす」として販売されている魚はカタクチイワシをはじめとするイワシの稚魚をさします。
しらすには稚魚でも成魚と同様ビタミンDやビタミンB12がしっかりと含まれていますが、加えて丸ごと食べられるしらすはタンパク質とカルシウムを豊富が豊富。
ビタミンDはカルシウムの吸収を助けてくれますので、ビタミンDもカルシウムも両方含むしらすは骨と歯の健康に良いとされています。
またビタミンB12は脂質やたんぱく質の代謝をサポートする働きがあり、不足する事で悪性貧血や神経障害、慢性疲労や運動時の息切れなどを起こすことが知れられていますので、そういったリスク回避のためにもしらすはお勧めの食材です。
新鮮なしらすの見分け方と保存方法

生しらすを購入する機会がありましたら、是非形がはっきりとして透き通っているものを選んで下さい。
特に足の早い生しらすは鮮度が落ちると身がふにゃっと張りがなくなります。
購入したらその日のうちに消費しましょう。
また、しらすは釜揚げすると身が白色、またキュッと腰が曲がるそうです。
一見するとまっすぐの方がきれいに見えるかもしれませんが、この「くの字」に曲がった釜揚げしらすは鮮度を見極めるパロメーターになります。
釜揚げしらすを選ぶなら是非くの字が多くあるものを選びましょう。
生しらす同様釜揚げしらすも鮮度が落ちやすいため冷蔵保存で2~3日以内に食べきりましょう。
食べきれない場合は冷凍保存もお勧め。
保存バックに入れ、空気を抜いた状態で1ヶ月程度冷凍保存可能です。
しらすのお勧めの食べ方

ここでは釜揚げしらすについてお話しします。
釜揚げしらすはそのままご飯に乗せて食べてもおいしいですが、お好みで刻みのりや大葉、ごまや刻みネギを散らしてワサビ醤油で頂くと、しらすの優しい味に加え、これらの風味が食欲のでない時など特におすすめです。
きびなご
きびなごの栄養素

体長10cmほどの小魚であるきびなごは年に2回旬がある魚としても有名です。
ひとつは冬の12月~2月、そしてもうひとつは産卵時期である5月~6月頃で、この時期は子持ちのきびなごも味わえます。
きびなごは小魚のため、丸ごと食べる事ができ、骨も気にならないという利点があります。
そのため、たんぱく質のほか、カルシウム、カリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミンD12、葉酸など特にミネラルを豊富に含みます。
新鮮なきびなごの見分け方と保存方法
新鮮なきびなごは触って張りのあるもの、銀色が鮮やかなものを選ぶとよいでしょう。
また、きびなごはアミエビを餌としているため、食べたアミエビが未消化で残っている場合はきびなごの腹が赤みを帯びた感じに見えます。
腹が赤いきびなごを食べても問題ありませんが、お腹に未消化の餌が残っていると鮮度落ちが早まるため、こうしてきたらすぐすぐに食べるようにする事が望ましいです。
きびなごのお勧めの食べ方

子持ちのきびなごが手にはいりましたら、是非丸ごと食べられる唐揚げや天ぷらがお勧め。
また、イワシのような青魚特有の風味はほぼなく淡泊でありながらも優しい旨味があります。
お刺身の場合、酢味噌が一般的ですが、ショウガ醤油やねぎ、大葉といった薬味と一緒に食べてもおいしいです。
メバル
メバルの栄養素

メバルは名の通り、大きく丸い目が特徴で、夜行性の魚のため、夜釣りで釣れるおいしい魚として釣り人たちに親しまれています。
特に冬から春にかけて産卵を行うため、産卵を終えた個体は体力を回復するために栄養を蓄え、その結果身に旨味が増しています。
メバルは白身魚の仲間ですが、青魚に豊富なEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)を多く含んでいます。
これら不飽和脂肪酸は脳の働きを活性化させる効果があり、記憶力や集中力を高めるだけでなく血液をサラサラにし、動脈硬化や高血圧のリスクを軽減する効果があるため健康維持にも役立ちます。
他にもたんぱく質や骨の健康を維持するビタミンD、疲労回復・美容ビタミンであるビタミンB群、さらには肝機能をサポートし生活習慣病を予防するタウリンなどまさに盛りだくさんに栄養素を含む魚です。
新鮮なメバルの見分け方と保存方法
メバルは1尾で選ぶ場合目がすんでいる事、えらが鮮やかな赤であること、体に光沢があることを目安にするとよいでしょう。
購入後その日のうちに頂くのが望ましいですが、大量に手に入った場合は冷凍保存も可能です。
袋や容器にメバルを入れ水をはった状態で冷凍(氷漬け)しましょう。
この時内臓を取り出すなど下処理は不要です。
氷漬けが難しい場合はラップなどで隙間なく包んで袋に入れて冷凍してください。
回答する場合は氷ごと水を張った容器に入れて解凍します。
メバルのお勧めの食べ方

メバルの煮つけは定番で、やはり文句なしにおいしいためおすすめです。
醤油:みりん:お酒を1:1:1の割合で煮込めば絶品につけの完成です。
また新鮮なメバルが手に入ったら、是非お刺身で召し上がってみてください。
身が引き締まり、弾力のある食感と甘みが特徴で白身魚ならではの上品な味わいが楽しめます。
ポン酢や醤油でシンプルに、またカルパッチョも良いですね。
その他塩焼や、唐揚げもふわっとした食感を楽しめるので是非味わってみてください。
鱧(ハモ)
ハモの栄養素

初夏から秋の産卵時期にかけて徐々に脂がのってくるハモ。
ビタミンB1、B2、B6などビタミン類をはじめ、カルシウムやリン、マグネシウムといったミネラルも豊富に含んでいます。
ビタミンB1は糖質の代謝を助け疲労回復や細胞の新陳代謝促進を促し、ビタミンB2は皮膚や粘膜の機能維持や成長に役立ちます。
また、抗酸化ビタミンであるビタミンCとEも含んでいるため、活性酸素の発生を抑え動脈硬化予防や皮膚や血管の老化防止、免疫力の向上も期待できます。
新鮮なハモの見分け方と保存方法
1尾で購入する場合は、身体に艶があり、色がはっきりとした茶色、目は黒々としているものを選びましょう。
また、ぬめりに透明感があるものが新鮮です。
骨切り処理が難しく、歯も鋭いため売り場で下処理をお願いし、購入する事をお勧めします。
切り分けたハモの身は冷蔵庫で保管する場合密閉容器に入れて保存します。
生の状態で保存する場合、2日を目安に使用しましょう。
ハモのお勧めの食べ方

ハモには長くて硬い小骨が多いため、細かい切り込みを入れて小骨を切る「骨切り」が必要です。
一見食べにくそうと印象を持たれるかもしれませんが、この骨切りがしっかりできれば、サッと湯引きして梅肉や辛子味噌を添えたり、お吸い物、土瓶蒸し、天ぷらなど様々な料理で楽しむことができます。
ホタルイカ
ホタルイカの栄養素

ホタルイカはその名の通り通り夜の海でホタルのように光っている事で有名です。
1杯丸ごと食べることができるため、その栄養をすべて体にとりいれる事ができます。
特に肝機能を整えてコレステロールの分解を助けるタウリンが豊富。
そのため、タウリンは肝臓に負担がかかっていたり、コレステロール値が高い生活習慣病で悩んでいる人にお勧めの栄養素です。
その他、強い抗酸化作用があるビタミンE、身体の成長に欠かせないビタミンA(レチノール)が非常に多く含まれていますので、免疫力を高めたり、老化予防にもおすすめの食材です。
新鮮なホタルイカの見分け方と保存方法
ホタルイカは傷むのが早いため、水揚げされてすぐに釜茹でされて流通しているものがほとんどです。
選ぶポイントとして生の場合は身が透き通っていて艶があり、目が黒く盛り上がっているものを選びましょう。
身が白っぽい物は鮮度が落ちてしまっています。
茹でられている場合は身が桜色で丸くふっくらとしているものを選びましょう。
赤茶色になっているものは鮮度が落ちてしまっています。
ホタルイカのお勧めの食べ方

ホタルイカに含まれるビタミンEやAはビタミンCと一緒に食べる事で吸収率がアップします。
ボイルしたホタルイカは酢味噌で食べるのが一般的ですが、ビタミンCが豊富な菜花を加え和え物にしてしまうのもおすすめです。
その他、炒め物やパスタに入れてもおいしく召し上がって頂けます。
5月と6月が旬の魚介類で食卓を彩ろう
いかがでしたでしょうか。
ご紹介した7選以外にもサザエやほたてなどの貝類、またウニも旬を迎えます。旬のおいしい魚介類が目白押しですね。
ご紹介してきましたように魚介類には人間の身体を作ったり、整えたり活動したりするための栄養素が豊富に含まれています。
是非毎日の食卓に旬の魚介類をとりいれてみてはいかがでしょうか。
煮込み料理の他、蒸し料理も得意な無水調理鍋PAPILLON、魚介の酒蒸しなど自然な食材の旨味を引き出してくれるお鍋をお求めの方にお勧めです。
どれも栄養価満点。そして旬の食材は味わい深く是非多くの方に積極的にとりいれていただきたいものです。
↓↓数量限定!魚介類を更に美味しくする無水調理鍋はこちら↓↓